当院の精神科
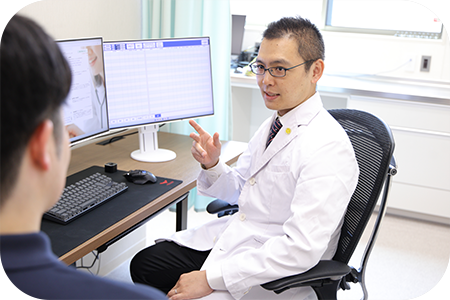
精神科・認知症治療の専門医が
適切な診療をご提供
精神科の専門知識と豊富な経験を活かし、患者さん一人ひとりに適した診療を提供しています。院長は、精神保健指定医や日本精神神経学会専門医・指導医、日本認知症学会専門医・指導医の資格を有しており、専門的な視点から的確な診断と適切な治療を行います。うつ病や不安障害、認知症など幅広い疾患に対応し、こころの不調に寄り添いながら、わかりやすい説明と丁寧な診療を心掛けています。患者さんが安心して相談できる環境を整え、専門的な治療を通じて健康を支えてまいります。

大府病院と連携し
入院対応や成人デイケアの
利用が可能
大府病院と連携し、必要に応じて入院の手配が可能です。さらに、大府病院の「精神科デイケア(ひまわり)」を利用できるため、外来診療に加え、社会復帰や認知症ケアを支える環境が整っています。患者さん一人ひとりに適した治療とサポートを提供し、安心できる医療体制を整えています。
当院では、かかりつけの患者さんを対象に訪問看護を実施しています。通院が難しいかたでも、ご自宅で適切な医療ケアを受けられるよう、専門のスタッフが訪問し、健康管理や服薬指導、精神的なサポートを行います。患者さんやご家族が安心して療養できるよう、医師と連携しながら細やかなケアを提供いたします。
訪問看護をご希望のかたは、お気軽にご相談ください。
老年精神科について

加齢に伴う
こころの変化に寄り添う
専門的なケアと治療
中年期から初老期以降のこころの不調や認知症に関するご相談を積極的にお受けしています。この年代は、青年期とは異なる精神疾患や、認知症をはじめとした神経疾患が原因となることもあり、身体面への配慮も欠かせません。精神科専門医に加え、内科や認知症に関する資格を持つ医師が、複雑な症状にも幅広く対応しています。ご本人はもちろん、ご家族のお悩みにも寄り添い、適切な治療や支援をご提案いたします。
 Trouble
Trouble
こんな場合はご相談ください
- 憂うつな気分がなかなか晴れない
- 怒りっぽく、イライラしやすい
- 原因不明の体調不良や痛み
- 幻覚や幻聴がある
- 不眠が続いている
- 落ち着かずそわそわする
- 被害妄想が見られる
- もの忘れが増えた
高齢者の代表的な疾患
認知症疾患
認知症とは、脳の神経細胞が損傷を受けることで、記憶力や判断力、思考力などが低下する状態を指します。代表的な原因には、アルツハイマー病、レビー小体型認知症、脳梗塞による血管性認知症などが挙げられます。進行する前に早期発見し、適切な対策を取ることが大切です。原因疾患によって治療法が異なるため、正確な診断を受けるには、専門外来での精密検査をおすすめします。
睡眠障害
年齢を重ねると、眠りが浅くなったり途中で目が覚めるなど、安定した睡眠がとりにくくなります。慢性的な睡眠不足は、高血圧などの生活習慣病を悪化させたり、うつ病といった精神的な不調を引き起こす要因となり、認知症リスクを高めることもあります。睡眠の質を低下させる原因を明らかにし、必要に応じた治療を行うことで、健康的な睡眠を保つことが大切です。
うつ病
うつ病は、長く続く気分の落ち込みや興味・意欲の低下が主な症状として知られる精神疾患です。しかし、高齢のかたでは、はっきりとした抑うつ感よりも、体調不良や原因不明の痛み、不安感や焦燥感といった形で現れることもあります。的確な診断には、経験豊富な専門医の診察が欠かせません。身体の検査で異常が見つからず、体調不良が続いてお悩みのかたは、ぜひ一度ご相談ください。
不安障害
過度な不安や恐怖により、日常生活に支障をきたす状態を不安障害と呼びます。代表的なものに、突然強い不安と身体症状が現れるパニック障害、人前で強い緊張を感じる社交不安障害、不安が慢性的に続き生活に影響する全般性不安障害などがあります。特に中高年期では、背景に身体疾患が隠れている場合もあり、慎重な診断が求められます。当院では、適切な評価と治療を行い、安心して日常生活を送れるようサポートします。
幻覚症
実際には存在しないものが見える(幻視)や、誰もいないのに声が聞こえる(幻聴)などの症状を指します。「幻覚症」という名称は、認知症による症状や精神疾患の一部として現れることもあり、幅広い病態を含む概念です。治療は、その症状を引き起こしている背景疾患に応じて進められます。適切な診断をもとに、原因に合わせた対処が重要です。
妄想性障害
現実とは異なる事柄を確信し、事実と誤った認識を持ち続けてしまう病気です。妄想の内容は、日常的に起こり得るものから非現実的なものまで幅広く、ご本人よりもご家族が対応に悩むケースも少なくありません。成人期では精神疾患として見られることが多い一方、初老期以降では神経疾患や脳の異常が背景にある場合もあります。神経学的・精神医学的な観点から適切に診断し、的確な治療方針を立てることが大切です。豊富な臨床経験を持つ医師による診察をおすすめします。
てんかん
てんかんは、脳の神経活動に異常が生じることで発作を繰り返す病気です。発作の種類や症状は多様で、けいれんや意識障害に限らず、一時的な記憶の混乱や幻覚などを伴うこともあります。高齢者では脳梗塞や認知症の影響で発症するケースも多く、若年層とは異なる背景疾患への注意が必要です。神経疾患と精神症状の両面から丁寧に診察し、適切な治療方針を立てることが重要です。十分な知識と経験を持つ専門医の診察を受けることをおすすめします。
成人精神科について

こころの悩み、
一人で抱えずご相談ください
成人期の患者さんを対象に、こころの不調やお悩みに寄り添った精神科診療を行っています。不安や気分の落ち込み、ストレスによる体調不良など、一人で抱え込まずにご相談ください。ご本人はもちろん、ご家族からのご相談にも対応し、丁寧にお話を伺った上で、症状やご希望に合わせた治療をご提案いたします。こころの健康を取り戻し、安心して過ごせる日々を一緒に目指しましょう。
 Trouble
Trouble
こんな場合はご相談ください
- 気分の落ち込みが続いている
- 些細なことでイライラしやすい
- 人混みにストレスを感じる
- なかなか寝つけない
- 疲れが抜けず、やる気が出ない
- 突然不安に襲われることがある
- 同じ思考にとらわれ、苦しくなる
- 気持ちが沈み、仕事に行くのがつらい
成人の代表的な疾患
適応障害
何らかのストレスが引き金となり、環境に適応できず心身のバランスを崩し、日常生活に支障をきたす状態です。主な症状として、気分の落ち込みや不安、不眠、いら立ちに加え、頭痛や動悸、吐き気などの身体的な不調が現れることもあります。この疾患の特徴は、明確なストレス要因が存在することです。仕事や学校などが原因となる場合、それらの場に行くことが困難になるケースも少なくありません。また、症状の強さには個人差があり、長期間強いストレスを抱えると、うつ病などの精神疾患へ移行する可能性もあります。適応障害の治療では、ストレスの軽減や除去を図りながら、社会復帰を目指すことが重要です。診断書が必要となる場合もあるため、お困りのことがあれば、一人で悩まず、お早めにご相談ください。
不眠症
不眠症は、眠りに関するさまざまな不調が続く病気です。寝つけない、途中で目が覚める、朝早く目覚めるといった症状があり、十分な睡眠が取れず、日中の生活に影響が出ることもあります。短期間であれば心配いりませんが、長期間続く場合は治療が必要です。ほかの病気が関係していることもあるため、まずは専門医にご相談ください。睡眠のお悩みに合わせた適切な対応を行います。
うつ病
うつ病は、気分の落ち込みや興味・意欲の低下が続くことで、日常生活に支障をきたす精神疾患です。仕事や人間関係のストレス、生活環境の変化などが引き金となり、眠れない、食欲がない、疲れやすいといった身体症状を伴うこともあります。ご本人が気づかないうちに症状が進行するケースもあり、早めの相談が大切です。気分の不調やからだのだるさが続く場合は、お早めに専門医へご相談ください。
双極性障害(躁うつ病)
双極性障害は、憂うつで無気力な「うつ状態」と、気分が高揚し活動的になる「躁状態」を繰り返す疾患です。多くの場合はうつ状態が長く続き、時に躁状態が現れます。躁状態では浪費や攻撃的な言動、性的逸脱などが見られ、生活や人間関係に支障をきたすこともあります。軽症の場合は気づかれにくく、周囲の理解が得られにくい傾向もあります。気分の波を安定させるためには、休養や薬物療法、精神療法などが重要です。気になる症状があれば、早めにご相談ください。
妄想性障害
妄想性障害は、事実とは異なる考えを強く信じ込み、周囲からの説明や指摘を受け入れられなくなる病気です。被害妄想や嫉妬妄想など、内容は現実的なものから突拍子もないものまでさまざまですが、本人は確信しているため、周囲の人間関係に影響を及ぼすこともあります。成人期ではストレスや性格傾向を背景に発症することが多く、精神科での適切な診断と治療が重要です。症状が気になる場合は、早めの受診をおすすめします。
統合失調症
統合失調症は、幻覚や妄想、考えのまとまりにくさなどを特徴とする脳の病気です。幻聴や妄想といった陽性症状に加え、意欲の低下や感情表現が乏しくなる陰性症状も見られ、日常生活や社会活動に大きな影響を与えます。本人が病気を自覚しにくいことも多く、周囲の家族や友人が異変に気づいて受診をすすめるケースもあります。治療は薬物療法と心理的支援を組み合わせ、長期的に行うことが重要です。気になる症状があれば、ぜひご相談ください。
パニック障害
パニック障害は、突然激しい動悸や息苦しさ、めまいなどの身体症状に襲われ、強い不安や恐怖を感じる病気です。「命の危険を感じるほどの恐怖」が急に起こることで、生活に支障をきたすこともあります。また、発作を経験した場所や状況を避けるようになり、外出が難しくなることもあります。治療には、薬による症状のコントロールと、恐怖や不安への心理的アプローチが重要です。お困りのかたは早めにご相談ください。
強迫性障害
強迫性障害は、自分の意思とは関係なく嫌な考えが頭に浮かび(強迫観念)、それを打ち消そうとして同じ行動を繰り返してしまう(強迫行為)病気です。汚れや確認へのこだわり、物がなくなる不安などにとらわれ、何度も手を洗ったり、不要な物を捨てられないといった行動が続きます。ご本人も無意味だと理解しつつ、やめられず苦しむことが多く、生活や人間関係にも影響を及ぼします。放置すると抑うつや引きこもりにつながることもあり、早めの専門的な治療が大切です。
社交不安障害
人前で話す、注目される、といった場面で強い緊張や不安、恐怖を感じる状態が社交不安障害です。症状が悪化すると、人と関わることを避けるようになり、外出や社会生活に支障をきたすこともあります。不安を感じている自覚はあっても、自力で克服できずに悩むかたが多いのが特徴です。一人で抱え込まず、早めに専門医へご相談ください。

